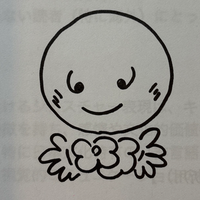以前、PIVOTの著者対談動画がこちらで紹介されていて、凄く興味が沸いたので、近著を読んでみた。非常に面白かったので忘れないうちに読書感想文。
(本書の内容を含みますので、これから読みたい方はご注意下さい。)
1 わかり味が深い「近現代史観の三形態」
Pivotの動画で、辻田氏は的確に戦後の近現代史観を三つに分類している。
①十五年戦争史観(満洲事変、日中戦争、大東亜戦争を一続きの戦争と考える→左派的史観)
②大東亜戦争肯定論(林房雄提唱。日本は欧米列強の植民地支配に対抗する為にアジア諸国全体を一つにまとめようとしたのだ→右派的史観)
③実証主義史観(下手な事を言うと左右から刺されるので一次資料を読み込むことに引き籠る→マニアックで一般に浸透しにくい イマココ!)
①は長らく義務教育の現場で教え込まれて来たものだし、②はその反動で起きた、古くは「新しい歴史教科書を作る会」か〜ら〜の、ネトウヨとかWGIP(War Gulit Information Program)といった、やや「陰謀論」も含む「日本無罪史観」みたいなもので、最後の③を聞いた時は思わず笑ってしまった。
私は、昔から歴史物が好きだったので、御多分に洩れず①〜③までを、ミーハーにひと通り「かぶれて来た」自覚がある。
ただ、どの史観をとっても「次に繋げるには(あの大失敗を繰り返さない為には)どうしたらいいのか?」という素朴な疑問にはあまり応えてくれていないように感じて来た。
「もう少し、全体像を分かりやすく、偏り無く、総覧出来ないかなぁ。」
と思っていた所に、本書の分量はちょうど良いボリュームと、これまでに無い切り口で、バラバラだった知識のピースを繋ぎ合わせてくれる良書であった。
2 第一次大戦から考える
辻田氏は「あの戦争」の始まりを見つめるならば「第一次大戦からだろう」と提唱している。
ちょうど、司馬遼太郎が「坂の上の雲」(日露戦争)までを描いて、そこから先の時代小説を絶対に書こうとしなかった事を考えると、とても順当な起点だと感じる。
(横道に逸れるけど、ノモンハン事件を書いてくれと司馬さんに懇願しても、絶対に無理だと拒否られたので「ならば僕が書きます!」と奮起したのが、当時、司馬さんの担当編集者だった半藤一利である事は有名な話。)
「明治維新の元勲が存命だった頃は、気心知れた仲間内で誰かの別荘に集まって国家の行末を決定することが出来た。その元勲達が居なくなって受験エリートが、国の舵取りをするようになると、彼らは決められたシステムの中でその通りに動くので、システムが抱えていた機能不全が露呈してしまった。」(ざっくり言えば、戦前の政治形態は権限が分散した構造で、内閣総理大臣であっても全権を掌握できない。)
「第一次大戦で、世界は「総力戦」の時代に入ってしまい、当時の政治家や軍人達は、その意味する所に戦慄した。日本は近代兵器に必要な天然資源は全く無く、日露戦争で一等国入りを果たしたものの、第一次対戦後の世界情勢は欧米列強が有利な形に進んでいる。」(日本は第一次大戦では、直接交戦国では無かったので、むしろ、軍需景気でウハウハに儲かったりしていた事も留意すべき点)
戦後、石原莞爾が東京裁判の尋問に訪れた米国人検事に対して
「戦犯を遡って断罪するなら、貴国のペリーが戦犯だろう。」
と混ぜ返して唖然とさせたエピソードは面白いが、確かに「ペリー来航で開国を迫られる」までは、日本も欧米列強の植民地政策の被害国になりかねなかったと言える。事実、不平等条約を結ばされて不当な扱いを受けていたのだし。
、、やはり、日韓併合あたりから「被害者から加害者へ転ずる分岐点」なのかもしれず、今でも「センシティブな外交問題」になっている事を考えると、この辺の「歴史的事実」をどう解釈するかで、左右の歴史観が分かれて行くのだと思う。
3 外国に残る「われわれ」の記録
本書で、一番面白かったのが、東條英機が首相に就任した後に行った「大東亜外交」と同じ場所に著者が実際に訪れて取材をした内容である。
戦況が悪化していたにも関わらず、1943年の1年間の間に、南京、上海、新京(現・長春)、奉天(現・瀋陽)、マニラ、サイゴン(現・ホーチミン)、バンコク、シンガポール、パレンバン、ジャカルタ、クチン、ラブアンへ、東條は精力的に外遊している。
各国が「日本統治時代」を歴史博物館にどの様な形で記録しているのか、その解釈の違いを知ろうという試みだったそうだが、明確に東條の外遊に言及していたのは、シンガポール、ラブアン、長春の3箇所で、他はその痕跡は無かったそうだ。(各博物館の解釈の詳細は本書に譲る)
辻田氏曰く、
「どの様な形であれ、どの国も歴史博物館(或いは戦史博物館)をしっかり作っているが、日本はそれに比較すると内容もボリュームも脆弱な様に思える。」
と語るが、確かに、「アンタッチャブルな問題」として避け続けて来た結果「普通の人が概要を知る」ような、手頃な場所が存在していないようにも感じた。
この辺りの記述は、国内にある関連施設(佐倉市の歴史民族博物館、靖国神社の遊就館、等々)を実際に取材した上で語られているので、かなり興味深い。
4 独裁者でも勤勉な官僚だけでも無い東條英機像
最後に、東條英機像が、これまでよりクリアになった事を述べたい。
東條が「独裁者と言い難い」ことは、近現代史を齧った人ならば自明のことだろう。
真珠湾攻撃当時の首相で、就任後、幾つもの役職を兼任して権力をグリップした事は間違い無いが、辻田氏曰く
「擬似独裁者の様に振る舞わないと、権限が散逸してしまった状態で、収拾がつかなかったからだ。」
と解説する。
そもそも、大日本帝国憲法の元では、総理大臣はあくまで、他の大臣と同列に「天皇を補弼」する一員でしか無い。今の総理大臣の様に、各大臣を任命したり更迭したりする権限が無いとなれば、自分が陸軍大臣も兼任して、内閣総辞職を防ごう(軍部大臣現役武官制を使って倒された内閣もあった)とした側面もあるわけだ。
改めて考えると、明治政府が日本の近代化を進めた時、その出発が「尊王攘夷」であり「天皇親政」を建前にしていた構造が、ここに来て機能不全を起こしていたんだと気付かされる。
では、東條英機は右派史観で言われたような「神経質な官僚タイプの能吏なだけだった」のかと言えば、それも実像を見誤ると本書は伝えている。
東條は、関東軍参謀長として満洲に赴任していた事もあり、その間に部隊を率いて内蒙古地域を占領した経歴がある。この時
「いうことを聞かない中国人は首を刎ね、然るのち米などを与えて、、云々」
と、後に秘書官達に「中国人の扱い方はこうするべきだ」と自分の経験を交えて語ったメモが残されている。
このメモは、東條を貶めようとする意図で公開されたのでは無く、その逆で「いかに、東條さんが用意周到で忠節の臣民だったか誤解を解いてもらう為に公開した」という。
現代感覚からすると、この違いに驚くが、注意すべきは「東條が特別に残虐」だった訳ではなく、
当時の日本人一般における中国人観がこのような感覚にもとづいていたということだ。掲げられていた理想と、現実の振る舞いとのあいだに横たわる深いギャップを、否応なく思い知らされる事例と言えるだろう。
とあって、非常に印象深かった。
南京大虐殺に関しても、昭和天皇の実弟だった三笠宮が中国大陸へ従軍した際の日記が平成に入って発見され、その中に明確に「日本軍の問題行動への批判」が書かれているそうで、
「そうか、、やっぱり、暴虐な振る舞いがあったのか。それは残念だな。」
と、認識を改める事が出来たのは良かったと思う。
この話題は、とりわけ今でも炎上し易い事案なので、どんどん語られなくなってしまう事も問題だろう。こうやって、批判を恐れずに、わかり易い形で取り上げた辻田氏の姿勢に感嘆の思いである。
そして、一番ハッとしたのが「あとがき」にあったこの一文
あの戦争は、たんなる過去のできごとではない。そこには、二重の意味において、特別な位置づけが存在している。
ひとつは、黄金時代の一大イベントとしての意味である。
どの国や文明にも、永遠に参照されつづける黄金時代というものがある。ここでいう黄金時代とは、よくも悪くも、その国や文明がもっとも大きな力を発揮し、歴史に爪痕を残した時代のことだ。スペインであれば、無敵艦隊が活躍したころだし、英国であれば、ヴィクトリア朝だろう。古代のローマ帝国や、チンギス・ハンのモンゴル帝国などもそれにあてはまる。
その枠組みで見れば、日本の黄金時代は昭和といってまちがいない。政治的にも経済的にも軍事的にも、あれほど日本が世界に影響を与えた時代はほかになかったし、今後も望みにくい。昭和の日本は、尽きせぬ教訓の泉として、小説やアートの豊穣な素材として、はたまた回帰すべき理想像あるいは反面教師として、これからも特権的に語られつづけるだろう。そして、あの戦争がその黄金時代のなかで中核をなす一大イベントだったことは論をまたない。
「うぉー!そんな事考えても見たことが無かった!」
と昭和生まれは思う訳だが、平成も終わり、令和の世になって振り返ると「確かにそうなのかも知れない」と、妙に感じ入ってしまった。
以上、本当はもっと興味深い内容が多い書籍なのだが、印象に残ったことに絞って述べてみた。
辻田氏は41歳とまだ若く、これまで、この界隈を牽引して来た重鎮達が、ここ数年、相次いで鬼籍に入った事に代わって健在化した「新しい流れ」とも感じられて、これからの活躍に期待したいと強く思う。(次は、昭和戦後史あたりを是非!)
(終)